目次
暗記が苦手だった私が感情記憶法に出会ったきっかけ
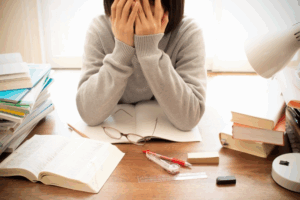
社会人になって3年目の頃、私は深刻な「暗記スランプ」に陥っていました。
IT業界に身を置く中で、新しいプログラミング言語やマーケティング用語を次々と覚える必要がありましたが、学生時代から使っていた「読んで書いて覚える」暗記法は、現場ではまったく通用しなかったのです。
特に印象に残っているのが、初めて外資系クライアントとの会議に出た時のこと。
会議中、先輩から「KPIの設計どうなってる?」と聞かれた瞬間、頭が真っ白に。
「…KPIって何の略でしたっけ?」と聞き返すこともできず、顔が真っ赤になりました。
この出来事をきっかけに、「ただ覚えるだけ」の勉強法に限界を感じ、本気で変わらなければと痛感したのです。
従来の暗記法での挫折体験
当時の私は、いわゆる“気合型暗記”に頼り切っていました。
- 単語カードでの反復
- 音読による丸暗記
- 一夜漬け
いずれも「その場しのぎ」の勉強法で、すぐに忘れるか、思い出すのに時間がかかる。
とにかく“覚えること”が苦痛で、自己評価では定着率は2割以下。
特に苦労したのは、略語やカタカナ語の暗記。
意味はわかっても、記憶の引き出しが開かないんです。
感情記憶法との運命的な出会い

転機が訪れたのは、ある日の通勤電車。
隣のビジネスマンが読んでいた本に「感情と記憶の関係性」についての記述が目に入り、ふと興味を持ちました。
「感情を伴った情報は、記憶に3倍定着しやすい」――その一文に衝撃を受けました。
「これ、試してみる価値あるかも」と思い、すぐに書店で同じ本を購入。
もともと心理学に興味があった私は、そこから数日間で関連書籍を5冊以上読み漁り、感情記憶法について徹底的に調べることにしました。
人間の脳は感情的な体験を伴った情報を、普通の情報よりも約3倍強く記憶するという研究結果が紹介されていたのです。
つまり、無機質な暗記ではなく、個人的な感情やエピソードと結びつけることで、記憶の定着率を劇的に向上させることができるということでした。
特に印象的だったのは、アメリカの心理学者が行った実験結果です。
被験者を2つのグループに分け、一方には単純な単語リストを、もう一方には個人的なエピソードと関連付けた単語リストを覚えてもらったところ、後者の記憶定着率が前者の2.8倍も高かったという報告でした。
最初の実践とその手応え
感情記憶法の理論に納得した私は、早速、業務に必要な用語で実験してみることにしました。
最初に選んだのは、「ROI(Return on Investment:投資収益率)」という用語。
これまでは「ROI=投資収益率」とただ機械的に覚えていたのですが、どうしても実務の中で使いこなせず、何度も調べ直す羽目に。
そこで私は、1年前に経験した“株式投資の失敗”をこの用語に結びつけることにしたのです。
当時、ネット証券で勢いだけの銘柄に手を出してしまい、3万円の損失を出した苦い思い出がありました。
「このときのROIは完全にマイナス。投資して損をしたという、あの悔しさを思い出せば絶対に忘れない!」
そう決めて、実際にこの感情とセットで覚えてみたところ、驚くべきことが起きました。
1週間後、何気なく上司からROIの説明を求められた際、反射的にスラスラと言葉が出てきたのです。
「たった1回の感情リンクで、こんなに違うのか…」
この体験が、私の学習スタイルを180度変えるきっかけになりました。
感情記憶法とは?従来の暗記法との決定的な違い

この方法は、単に「エモい気持ちで覚える」だけではありません。
情報と個人の記憶・感情・体験を“強く”結びつけることで、脳の深層に記憶を刻み込むテクニックなのです。
例えば、学生時代にどうしても覚えられなかった「photosynthesis(光合成)」という単語。
私はこれを、「小学生の頃に祖母の庭で育てたミニトマトの思い出」と結びつけました。
陽の光を浴びた葉っぱがキラキラしていた記憶と、「photo=光」「synthesis=合成」が自然にリンクし、以後一度も忘れたことがありません。
従来の暗記法が効果的でない理由
多くの人が学生時代から使ってきた「反復暗記法」。
私も例に漏れず、何度も書いて、声に出して、覚えることに全エネルギーを注いでいました。
でも、社会人になってから気づいたのです。
「思い出せない記憶は、意味がない」と。
実際、プレゼンやミーティングの現場で「聞いたことはある…けど、説明できない」という場面に何度も直面しました。
これは、以下のような従来型暗記法の弱点が原因です。
- 短期記憶に依存:一時的には覚えても、すぐに忘れてしまう
- 機械的な処理:理解よりも“丸暗記”が目的になり、応用が利かない
- 感情の欠如:脳が“重要な情報”として扱わないため、記憶に残らない
当時、プロダクトマネージャーに昇進したばかりの私は、毎日新しい専門用語のシャワーを浴びていました。
でも、記憶に定着しないせいで、話についていけず、劣等感すら感じる日々でした。
感情記憶法の科学的根拠
「本当にそんなに効果があるの?」と思う方もいるかもしれません。
でも、感情記憶法はただの精神論ではなく、脳科学的にも裏付けのある学習法なのです。
脳には「扁桃体(へんとうたい)」という感情処理を担当する部位があり、ここが活性化すると、記憶を司る「海馬」がより強く働くようになります。
つまり、感情を伴った情報は、脳にとって「重要なもの」と判断され、記憶の回路に強く残る。
実際、ある心理実験では、単語リストを覚えるグループと、個人的な感情と結びつけたグループとで比較したところ、後者の記憶定着率は2.8倍にもなったという結果が出ています。
| 記憶法 | 記憶の種類 | 定着期間 | 応用力 |
|---|---|---|---|
| 反復暗記法 | 短期記憶中心 | 数日~1週間 | 低い |
| 感情記憶法 | 長期記憶中心 | 数ヶ月~数年 | 高い |
感情記憶法の基本メカニズム
感情記憶法が効果を発揮するのは、「記憶したい情報」に以下の3つの要素を組み合わせるからです。
1. 個人的な体験との関連付け
私は「photosynthesis(光合成)」という単語をどうしても覚えられなかった大学時代、ある日ふと、小学生の頃に祖母の家で育てた朝顔の記憶がよみがえりました。
水やりをしながら祖母に「太陽があるから育つんだよ」と教えてもらった、その時の温かさを思い出し、
「photo=光」「synthesis=合成」→ “太陽の光で植物が育ったあの庭”と記憶をつなげたところ、二度と忘れなくなったのです。
2. 感情的なインパクトの付与
ただ覚えるのではなく、嬉しかった、悔しかった、驚いたなどの感情を強くリンクさせるのがポイント。
私の場合、「API(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)」という用語を覚える時、「まるで通訳者のように、別々のアプリ同士が会話してる!」と気づいた時の驚きと納得感が、一気に記憶定着に結びつきました。
3. 五感を使った記憶の強化
記憶をさらに強固にするためには、視覚・聴覚・触覚などの感覚も巻き込みます。
たとえば、私は「ROI(投資収益率)」を覚えるとき、金色のコインがくるくる回る映像を頭に浮かべました。
さらに「投資失敗の悔しさ」を思い出しながら、手でコインを握るような動作を加え、声に出して「アール・オー・アイ」と唱える。
この多層的な記憶アプローチが、記憶定着をぐっと底上げしてくれるのです。
私が実践している感情記憶法の基本ステップ
ここからは、私が5年かけて試行錯誤しながらたどり着いた「感情記憶法の実践ステップ」をご紹介します。
最初はうまくいかないこともありましたが、今では新しい専門用語でも8割以上の定着率を誇る、自分だけの“鉄板ルーティン”になっています。
ステップ1:記憶対象の感情フックを見つける
最初のポイントは、「この言葉、自分のどんな経験や感情と結びつけられるか?」という問いかけです。
たとえば、「KPI(Key Performance Indicator)」という用語。
かつて私は、あるプロジェクトでKPI未達が続いて上司に詰められたことがありました。
この苦い経験に「K(恐怖のK)」「PI(Perfectと呼ばれる快感)」という感情を結びつけることで、言葉そのものが“感情を持った存在”になったのです。
具体例:KPIの場合
- 恐怖の感情:「KPIが達成できないと上司に怒られる恐怖のK」
- 達成感の感情:「Perfect!と言いたくなるPI」
- 視覚的感情:「Indicatorは『指し示す』→人差し指で指している自分の姿」
この方法で、単なる英単語の羅列だった「KPI」が、私の実体験と感情に結びついた生きた知識として定着しました。
ステップ2:五感を使った感情の増幅
人間の脳は、「複数の感覚」が同時に刺激されると、情報をより強く記憶します。
たとえば私の場合
- 「ROI」は、金色のコインが回る映像(視覚)
- 「API」は、「あっぴー」と口に出す可愛い響き(聴覚)
- 「フレームワーク」は、両手で四角を作る動作(触覚)
といった具合に、感情×五感の組み合わせが、記憶の深さを劇的に変えました。
| 感覚 | 活用方法 | 私の実践例 |
|---|---|---|
| 視覚 | 色彩やイメージと結びつける | 「ROI(投資収益率)」を金色のコインが回転する映像で記憶 |
| 聴覚 | 音の響きや語呂合わせを活用 | 「API」を「あっぴー」という可愛い響きで覚える |
| 触覚 | 手の動きや身体感覚と連動 | 「フレームワーク」を両手で枠を作る動作と一緒に記憶 |
認知科学の研究でも、複数の感覚を同時に使うことで記憶定着率が向上することが証明されています。
特に効果的だったのは、新しい用語を覚える際に必ず声に出して読み、同時に関連する手の動きを加えることでした。
この方法により、従来の黙読だけの暗記と比べて記憶定着期間が約3倍長くなったことを実感しています。
ステップ3:個人的エピソードとの結合
感情記憶の真髄は、「あなた自身の物語」を織り交ぜること。
私は「アジャイル開発」という言葉を初めて聞いた時、高校の文化祭準備の苦い思い出が浮かびました。
綿密な計画を立てすぎて当日バタバタになった、あの経験。
「最初から完璧を求めるより、小さく作ってすぐ改善したほうがよかったよな」と気づいた時、アジャイルの本質が感情と共にスッと頭に入ってきたのです。
ステップ4:感情記憶の定期的な再活性化
作った感情記憶は、定期的に再生して“長期保存”します。
私のルーティン
- 通勤時間:電車で昨日覚えた用語を頭の中で再現
- 休憩中:コーヒー片手に、1週間前の記憶を思い出す
- 就寝前:その日の新しい用語と結びつけた感情を整理
これを習慣化するだけで、3ヶ月前に覚えた言葉でも、まるで昨日のことのように鮮明に思い出せるようになりました。
この再活性化により、一度作った感情記憶が薄れることなく、むしろ時間が経つほど強固になっていくことを実感しています。
専門用語を覚える具体的な感情の結びつけ方

私がプロダクトマネージャーとして働く中で、特に役立ったのが「感情の種類によって記憶定着率が違う」という発見です。
この気づきから、私は感情別のアプローチ法を使い分けるようになりました。
【驚き・発見の感情】
記憶定着率が最も高くなるのが、“ハッとした感覚”。
たとえば「API(Application Programming Interface)」を覚えるとき、
「まるでアプリ同士の“通訳者”じゃん!」と気づいた瞬間の驚きが、記憶にガツンと刻まれました。
今でも「API=通訳」のイメージと感情が瞬時にセットで蘇ります。
【恐怖・不安の感情】
ネガティブ感情も、実は強力な記憶ブースター。
「デッドロック(Deadlock)」という概念を学んだ時、
「この状態になるとシステムが永遠に止まる…!」という恐怖心をイメージと共に焼き付けました。
こうしたインパクトは、無機質な定義よりはるかに強く記憶されます。
個人的エピソードとの組み合わせ術
感情に“リアルな自分の物語”を組み合わせると、効果はさらに倍増します。
| ステップ | 内容 | 実践例 |
|---|---|---|
| 1. 用語理解 | 専門用語の定義を調べる | 「スクラム=チームで進める柔軟な開発手法」 |
| 2. 類似体験の発掘 | 過去の似た体験を思い出す | 文化祭の出し物づくりでの役割分担 |
| 3.感情の特定 | その時の感情を思い出す | チームで達成した時の喜び |
| 4. 結びつけ | 用語とエピソードをリンク | 「スクラム=文化祭の準備と同じ協力体制」 |
この方法で覚えた用語は、半年経っても、身体感覚とともにスムーズに引き出せます。
重要なのは、自分だけの体験と結びつけることです。
他人の体験談では感情記憶の効果は半減してしまいます。
効果的な感情の作り方
私も最初は「嬉しい」「楽しい」といった感情を使っていましたが、どうも記憶に残りにくいと感じていました。
重要なのは、感情をできるだけ「鮮明」に、かつ「身体感覚」と一緒に思い出すこと。
具体例
- 「楽しい」→「初めてクイズに正解したときのガッツポーズ」
- 「驚き」→「まさかこんな仕組みだったの!?と口を開けてしまった瞬間」
- 「怖い」→「会議で質問されて何も答えられなかった時の冷や汗」
こうした“身体感覚”まで伴った記憶は、1回の記憶でも何度も呼び出せるほど強く残ります。
さらに、感情に身体的な感覚を加えると効果が倍増します。
「データベースのインデックス」を覚える際、「辞書の索引のように情報を素早く見つけられる」というイメージに「本をパラパラめくる手の感覚」を結びつけました。
視覚・聴覚・触覚を組み合わせることで、記憶の定着率が格段に向上したのです。
この感情記憶法を使い始めてから、専門用語の暗記時間が従来の3分の1に短縮され、長期記憶への定着率も80%以上を維持できるようになりました。
感情記憶法の落とし穴と対策

感情記憶法を使い始めてから、私は暗記に対するストレスが激減し、記憶の精度も大きく向上しました。
しかし、実は最初のうちは“うまくいきすぎる”ことの罠にハマってしまったんです。
「もうどんな言葉も覚えられる!」
と調子に乗って感情を詰め込みすぎた結果、逆に記憶が混乱し、やる気を失う時期がありました。
ここでは、私が実際に経験した“感情記憶法の落とし穴”と、それをどう乗り越えたかを正直に共有します。
ネガティブ感情に偏りすぎた失敗体験
私は最初、「記憶に残りやすい=ネガティブ感情が強い」と考え、過去の恥ずかしい失敗や怒られた経験ばかりを用語に結びつけていました。
たとえば
- 「リスク管理」=過去に炎上したプロジェクトの恐怖
- 「ステークホルダー」=上司に詰められたプレゼンのトラウマ
最初は記憶に残りましたが、徐々に「この言葉を思い出すだけでイヤな気分になる」という副作用が…。
やがて学習自体がストレスになり、関連する分野を避けるようになってしまったのです。
感情記憶法は確かに効果的ですが、使用する感情のバランスが重要だということを痛感しました。
感情の強度調整を間違えた事例
もうひとつのミスは、「感情を盛りすぎて逆効果になった」ケース。
たとえば「コンバージョン率」を覚えるために、人生初の大成功プレゼンの達成感とリンクさせたことがあります。
ところが、その強烈な感情が毎回呼び起こされるせいで、逆に他の言葉が頭に入らなくなったんです。
感情が強すぎると、“記憶の独り占め”が起きてしまうんですね。
感情記憶において重要なのは、記憶定着に必要な程度の適度な感情強度を保つことです。
強すぎる感情は学習の妨げとなり、弱すぎる感情は記憶効果を発揮しません。
実践的な対策とバランス調整法
こうした経験を経て、私は以下のようなバランス調整ルールを取り入れました。
| 問題点 | 対策 | 具体例 |
|---|---|---|
| ネガティブ感情の使いすぎ | 感情の比率をポジティブ7:ネガティブ3に調整 | 「達成感」や「安心感」を中心に使う |
| 感情の強さが極端 | 感情の強度を5段階中3前後に設定 | 「ちょっと嬉しい」「少し悔しい」レベルに抑える |
| 同じ感情の使い回し | 同じ体験は最大3つの用語までに制限 | 使いすぎると記憶が混線するため |
また、月に1度は「感情記憶の棚卸し」をして、使っている感情のバランスや強度を見直すようにしています。
この習慣により、感情記憶法の効果を長期間維持できるようになりました。
これらの失敗と対策を通じて学んだのは、感情記憶法は単に感情と情報を結びつければよいというものではなく、感情の質と量を適切にマネジメントする技術だということです。










