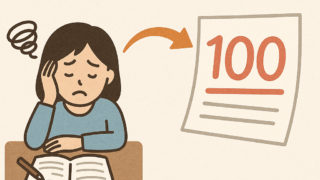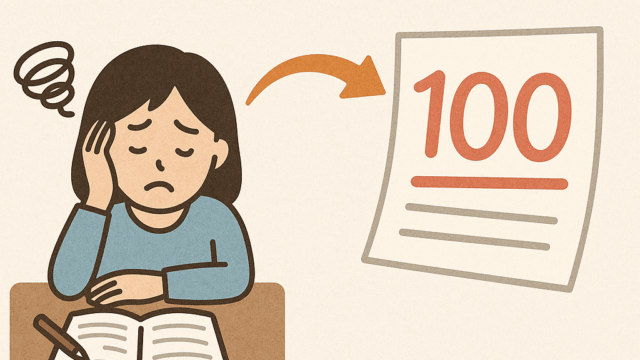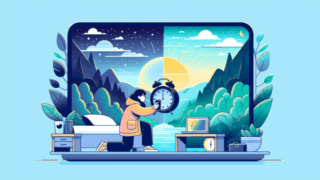「お前さ、ちゃんと覚えたんだろ? じゃあ、何で出てこないんだよ?」
大学受験直前の模試で大失敗し、焦って泣きそうになっていた私に、塾の講師が苦笑いしながら言ったひとことです。
当時の私は、ひたすら英単語を詰め込み、公式を反復し、ノートを暗記カードで埋め尽くす…そんな“努力型の暗記人間”でした。
でも本番になると、頭が真っ白。
あれだけ覚えたはずの知識が、使えない。繋がらない。出てこない。
何度同じ失敗を繰り返しても、やり方を変える勇気がなかったんです。
そんな私の学習観を180度変えたのが、たったひとつの言葉でした。
「それって、なんで?」
この“なんで?”という問いを3回繰り返すだけで、今までの「覚えているつもり」が、「分かっている実感」へと変わったんです。
本記事では、私がどのようにしてこの“深掘り学習法”と出会い、暗記地獄から脱出できたのか、そして現在の仕事にどう活きているのかを、体験ベースでお伝えします。
目次
「なぜ?」を3回繰り返す学習法に出会うまで

私は現在、IT企業でプロダクトマネージャーとして働いていますが、「勉強の仕方が分からない」という悩みは、実は社会人になってからもずっと抱えていました。
思い返せば大学受験時代。
私は「とにかく暗記すればなんとかなる」と信じて、毎日100単語を目標に英単語帳を繰り返していました。
通学中も食事中も、スマホで英単語アプリを眺める日々。
夜になると疲れてウトウトしながらも、「今日の分はやらなきゃ…」とノルマをこなしていました。
でも、模試の結果はボロボロ。
単語テストでは80点取れても、長文読解は40点台。
覚えたはずの単語が文章に出てきても、文脈で意味が取れないんです。


テスト中、そう思いながら頭が真っ白になる感覚を、今でもはっきり覚えています。
数学も同様でした。
公式は全部暗記していたのに、出題パターンが少し変わるだけで解けない。
応用問題になると、まるで初めて見る問題かのように、手が止まってしまう。

そんな混乱を何度も味わいました。
正直、「こんなに頑張ってるのに、なんで結果が出ないんだろう」と、自信を失いかけていた時期もありました。
暗記の限界と“本当の理解”の違い
大学卒業後、IT企業に就職して、プログラミングやマーケティングなど、新しい知識を次々に学ばなければならない状況に。
でも、ここでも私はつまずきました。
新しい言語の構文を必死に覚えても、実際の現場ではまったく応用できない。
参考書を一通り読んだのに、「これ、どうやって使えばいいの?」と悩むことばかり。
そして迎えた転機が、入社3年目。
プロダクトマネージャーへの職種転換を目指していた時期に、マーケティングの知識を一から学ぶ必要が出てきました。

限られた時間で効率よく学ばなければならない中、私は“暗記頼み”の学習ではもう限界だと痛感しました。
そんな時に出会ったのが、認知科学の本に書かれていた「深掘り学習」という考え方でした。
「なぜ?」を繰り返すことの重要性を実感した瞬間

「顧客セグメンテーションって、要するに分類でしょ?」
マーケティングの勉強を始めたばかりの頃、私は正直そんなふうに軽く考えていました。
定義を暗記して、「年齢・性別・年収で分けるんだよね」と思って満足していたんです。
でも、ある日。
実際のプロジェクトで「この商材に合うセグメンテーション軸を考えてほしい」と言われた時、私は完全にフリーズしました。


このとき初めて、「知っている」と「使える」の間に大きなギャップがあることに気づいたんです。
そこで試してみたのが、あの“深掘り学習法”でした。
実際にやってみた「なぜ?」の3ステップ
私は、顧客セグメンテーションというテーマに対して、3回の「なぜ?」を投げかけてみました。
・1回目の「なぜ?」
なぜ顧客を分類する必要があるのか?
→ 効率的にマーケティング施策を行うため。リソースを集中投下できる。
・2回目の「なぜ?」
なぜリソースを集中させる必要があるのか?
→ すべての顧客に同じメッセージを出しても響かない人がいるから。
・3回目の「なぜ?」
なぜ同じメッセージでは響かないのか?
→ 顧客ごとに価値観やニーズ、購買動機が異なるため。
この3段階を通して、私はようやく「顧客を分類する」という行為が、単なる作業ではなく、“相手に届く言葉を選ぶための戦略的アプローチ”だと理解しました。
この瞬間、マーケティングが「使える知識」へと変わったのです。
自分の中で「腑に落ちた」感覚
それまでは、どこか他人事だったマーケティング理論。
でも、「なぜ?」を繰り返したことで、理論と現場が一本の線でつながった感覚がありました。
この体験が、私にとって深掘り学習法の“最初の成功体験”でした。

この感覚を得てから、私はどんなテーマでも「なぜ?」から入るクセがつくようになりました。
「なぜ?」を3回繰り返す深掘り学習法とは何か

私が「なぜ?」を3回繰り返す深掘り学習法に出会ったのは、ある新規プロジェクトでプロジェクト管理ツールを新しく習得しなければならなかったときでした。
そのツールにはガントチャートやタスク管理などの機能がありましたが、最初は操作マニュアルを読んで「手順を覚えること」に集中していました。
でも…覚えたはずなのに、現場では動けない。


そんなとき、ふと頭に浮かんだのが、以前読んだ認知科学の本に出てきた「5 Whys(5回のなぜ?)」という問題解決法。

そう思い、私は学習の際に“3回のなぜ”を投げかけてみることにしたんです。
なぜを3回繰り返すと見えてくる“理解の層”
この学習法の面白いところは、「知識に奥行きが出る」ことです。
ただ覚えるのではなく、「なぜそうなっているのか?」を掘り下げることで、以下のように理解が立体化していきます。
| 段階 | 質問内容 | 得られる理解 |
|---|---|---|
| 1回目のなぜ | 「なぜこの現象が起こるのか?」 | 直接的な原因・仕組みの理解 |
| 2回目のなぜ | 「なぜその原因が存在するのか?」 | 背景・前提条件の理解 |
| 3回目のなぜ | 「なぜその背景が重要なのか?」 | 本質的な価値・意義の理解 |
実際に私がプロジェクト管理システムを学習した際の例をご紹介します。
1回目のなぜ:「なぜガントチャートを使うのか?」
→ プロジェクトの進捗を視覚的に管理するため。
2回目のなぜ:「なぜ視覚的な把握が重要なのか?」
→ 複数人で進行状況を共有しやすく、遅延リスクを早期に察知できるから。
3回目のなぜ:「なぜチーム全体で共有する必要があるのか?」
→ プロジェクトは連携プレー。情報共有が遅れると、手戻りや納期遅延につながるため。
ここまで掘り下げたことで、私は「ガントチャートを使う理由」を自分の言葉で説明できるようになりました。
結果、別の管理ツールに切り替わっても、「機能の目的」が分かっているから応用がきくようになったのです。
具体的な実践方法と手順
「なぜ?」を3回繰り返す──それだけ聞くと簡単そうに思えますが、実際にやってみると、意外と“深掘りのコツ”が必要です。
私自身も最初は「2回目の“なぜ”が出てこない…」と手が止まることがありました。
でも、何度か繰り返すうちに、だんだんと問いの“深さ”や“角度”を変える感覚が身についてきたんです。
以下に、実際に私が使っている手順とコツをご紹介します。
ステップ1:「表面的な知識」に疑問をぶつける
まずは、今まさに学んでいる内容や、これから使う知識に対して「そもそも、なぜこれが必要なのか?」と問いかけます。
これは一番わかりやすく、すぐに答えが出てきやすい段階です。
例:なぜガントチャートを使うのか?
→ 進捗状況を視覚的に確認したいから。
ステップ2:「背景や構造」に切り込む
次に、その理由の背景にある仕組みや前提に目を向けます。
例 : なぜ視覚的な確認が必要なのか?
→ チームで共通認識を持つため。プロジェクトに関わる人が多いから。
ここでのコツは、「それって誰のため?」「それがなかったら何が起きる?」と考えてみること。
これにより、ただの暗記だったものが、状況や文脈と結びつきはじめます。
ステップ3:「その背景がなぜ重要か」を問う
最後は、その“背景”が学習対象にどう影響しているかを問うことで、本質的な価値や意義にたどり着きます。
例 : なぜチームで共通認識を持つことが重要なのか?
→ 情報のズレや見落としが、プロジェクト全体の失敗につながるから。
この段階に入ると、「なぜ学ぶのか?」「この知識をどう使うのか?」が自分ごととして腑に落ちてきます。
紙に書くと“気づき”が加速する
私が個人的におすすめしたいのは、この3つの「なぜ?」をノートや付箋に書き出すことです。
書きながら「本当に分かってる?」と自分に問い直すことで、見落としていた視点に気づいたり、「あ、これって前に学んだあれと同じ構造かも」と過去の知識とつながる感覚が得られることもあります。
従来の暗記学習との決定的な違い
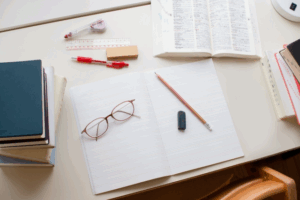
「覚えているのに、使えない」
かつての私は、このフレーズそのままの学習者でした。
参考書を読み込んで、用語も手順も何度も書いて覚えた。
それなのに、いざという場面では手が止まり、応用がきかない。
それが本当に悔しかった。
でも、「なぜ?」を3回繰り返す深掘り学習を取り入れてから、明らかに学習の質が変わったんです。
深掘り学習を取り入れる前の私
たとえば、ある日、プロジェクトで新しい管理ツールを導入することになりました。
私のタスクは、操作マニュアルを読んで基本操作をマスターし、チームに使い方をレクチャーすること。
当時の私は、操作手順を忠実にメモし、それを“丸暗記”して準備を整えました。
でも──説明の途中で、誰かにこう聞かれたんです。
「これって、なんでその設定が必要なんですか?」
…詰みました。
手順は覚えてる。
でも、なぜそのステップが必要なのかは、考えたことがなかった。
深掘り学習に切り替えた後の変化
同じような場面が後日もう一度訪れたとき、私は「なぜこの設定があるのか?」から自分で深掘りして理解していました。
結果、以下のような“変化”が起きました。
| 学習前(暗記ベース) | 学習後(深掘り学習) |
|---|---|
| 操作手順を暗記しても状況が変わると対応できない | 「目的」を理解しているから手段が変わっても対応可能 |
| 予期しない質問に答えられない | 背景や意義を説明できるようになり、説得力が増す |
| 別のツールに変わると一からやり直し | 考え方が頭にあるから応用が効く |
特に印象的だったのは、新しいプロジェクト管理ツールに切り替わったときのこと。
以前なら「また一から覚え直しか…」と絶望していたと思いますが、深掘り学習の経験があったことで、

というふうに、根本の「考え方」をそのまま再利用できたんです。
点ではなく“面”で理解する力
この手法の最大のメリットは、知識を“点”ではなく“面”で理解できることです。
1つの知識が、他の知識とつながり、文脈の中で「使えるもの」として機能する。
だから、ツールが変わっても、内容が変わっても、原理が同じなら迷わず動けるようになるんです。
実際に私が深掘り学習法を試してみた最初の体験談
私が「なぜ?」を3回繰り返す深掘り学習法を、初めて本格的に試したのは、プロダクトマネージャーとして働き始めて2年目の頃でした。
その頃ちょうど、新しい業務でデータベース設計を学ばなければならなくなったんです。
でも、参考書を読んでも、「こういうルールです」「この形にすべきです」といった説明ばかり。


そうやって“表面的な理解”だけでなんとなく納得していた私は、実務の場面で完全に詰まりました。
きっかけは「正規化」という壁
あるとき、実際のプロジェクトで、顧客データベースの設計を担当することになりました。
その設計レビューの場で、上司からこう問われたんです。
「なぜこの構造にしたの?」
「このテーブル、正規化はどこまで考えてる?」
私はそのとき、何も答えられませんでした。
参考書に書いてあった通りにやっただけ──
でも、その“理由”を、自分の言葉で説明する準備がまったくできていなかったんです。
「なぜ?」を3回重ねて見えてきた“本質”
焦った私は、以前読んだ認知科学の深掘り学習の手法を思い出し、次のように自問してみました。
1回目の「なぜ?」:なぜ正規化が必要なのか?
→ 「データの重複を減らすため」──これはよくある模範解答。
でも、この段階ではまだ表面的。
2回目の「なぜ?」:なぜ重複を減らす必要があるのか?
→ 重複があると、データを更新するたびに複数箇所を修正しなければならず、更新漏れや不整合が発生するから。
ここで私は、以前のプロジェクトで「住所変更が一部の画面に反映されなかった」というバグを思い出しました。
3回目の「なぜ?」:なぜデータの不整合が問題になるのか?
→ 顧客情報が誤っていれば、ビジネス上の判断ミスやクレームにもつながる。
つまり、システムの信頼性そのものが失われてしまう。
このプロセスを経て、「正規化とは単なる整理術ではなく、ビジネスを支える“信頼性の設計”なんだ」と理解できた瞬間──正直、鳥肌が立ちました。
深掘りしたことで得られた変化
その後、同じようなレビューの場で、「なぜこの設計にしたのか?」と聞かれたとき。
私は、構造の理由だけでなく、「なぜこの正規化レベルが必要だったか」をビジネス観点で説明できるようになっていました。
以前なら「…参考書にそう書いてあったので」という回答しかできなかった自分が、しっかりと背景を語れるようになっていたんです。
これは、深掘り学習法を通じて得た「自分の言葉で理解する力」の、最初の実感でした。
プログラミング学習で実践した具体的な「なぜ?」の質問例
深掘り学習法が、自分の中で“確信”に変わったのは、プログラミング学習で実践したときでした。
特に印象に残っているのが、JavaScriptの配列メソッド「map」を学んでいたときのことです。
正直、それまでは「mapは、for文よりちょっとスマートに書けるやつ」くらいの理解で止まっていました。
でも、実務で大量のデータを扱う処理に直面したとき、「この使い方、本当に正しいのか?」と不安になったのです。
そこで私は、mapメソッドに対して3回の「なぜ?」を実践してみました。
【1回目の「なぜ?」- 基本機能への疑問】
「なぜmapは新しい配列を作るのか?元の配列を変えてもよさそうなのに…」
この疑問から、私は“イミュータブル(不変性)”という概念に初めて出会いました。
mapは元のデータを壊さないことで、予期しない副作用を防ぐという設計思想のもと作られている。

と納得できた瞬間でした。
【2回目の「なぜ?」- 設計思想への疑問】
「なぜ不変性がそれほど重要なのか?」
ここから、複数人でコードを扱う開発環境では、同じデータを複数の関数が同時に参照・操作することで、意図しないデータの上書きやバグが発生しやすくなるという問題を学びました。
特に、以前参加したプロジェクトで「ある修正が他の機能に影響した」ことを思い出し、

と、現実の出来事と知識がリンクしました。
【3回目の「なぜ?」- 応用への疑問】
「この特性を活かすと、どんな複雑な処理が簡潔になるのか?」
この問いから、私は関数型プログラミングの考え方に出会い、「map」「filter」「reduce」などを組み合わせるメソッドチェーンが非常に強力なツールだと理解しました。
結果として、大量のデータ処理や整形を、数行のコードで、可読性高く、安全に書けるようになりました。
実践によって得られた“知識の質”の変化
この深掘り学習プロセスを通じて得られた具体的な成果をまとめます。
| 質問段階 | 発見した知識 | 実践での活用 |
|---|---|---|
| 1回目 | イミュータブル設計の概念 | 元データを守ることで、バグの発生を回避 |
| 2回目 | チーム開発におけるデータ競合のリスク | 安全で保守しやすいコード設計ができる |
| 3回目 | 関数型プログラミングの強み | 可読性・再利用性の高いコードを実装 |
この3段階の問いかけによって、単なる“構文”だったmapが、実務で応用できる「武器」へと変わりました。
応用力が身についた実感
その後、PythonやSwiftなど別の言語でも「配列操作」に出会ったとき、私は自然とこう考えるようになっていました。


つまり、「言語の違い」に惑わされることなく、“考え方”をベースに応用ができるようになっていたんです。
これこそ、深掘り学習で得られた最大の成果だと感じています。
表面的理解から本質的理解への変化を実感した瞬間
深掘り学習を続けるうちに、私は少しずつ「知識の扱い方」が変わっていきました。
でも、それが本当に“血肉になった”と実感できたのは、あるマーケティングのプロジェクトがきっかけでした。
新しい商品企画の立ち上げに関わり、顧客分析をベースに戦略を組み立てるフェーズ。
その中で、「ターゲット層を明確にするためのセグメンテーション案を出してください」と言われました。
以前の私なら──

…そんな“覚えた知識”をそのまま当てはめていたと思います。
でも、このときは自然と、自分にこう問いかけていたんです。
再び3回の「なぜ?」が力をくれた
1回目の「なぜ?」:なぜ顧客セグメンテーションが必要なのか?
→ 限られたリソースを、もっとも効果の高い顧客に集中させるため。
2回目の「なぜ?」:なぜリソース集中が必要なのか?
→ 全員に同じアプローチをしても、ニーズが異なれば届かないから。
3回目の「なぜ?」:なぜ同じアプローチでは届かないのか?
→ 顧客ごとに価値観・課題・購買行動が異なっているから。
このプロセスを踏んだことで、私は「ただ属性で分類するのでは不十分だ」と気づきました。

そう考え、私は「ライフスタイル」や「情報収集パターン」を軸とした分類案を提案しました。
「知っている」から「考えられる」へ
その提案はクライアントにも好評で、最終的には実際のマーケティング施策にも活用されました。
何より、自分の中で感じた変化が大きかったんです。
以前は、

という反応だったのが、今では、

と、“理解”が“判断力”に変わった実感がありました。
他分野への応用も広がった
この学習法の面白いところは、1つの分野で身につけた“問い方”が、他の分野でもそのまま使えること。
例えばチームマネジメントにおいて──
「なぜこのメンバーには同じ指示が響かないのか?」
→ 「なぜその価値観を持っているのか?」
→ 「なぜその背景を理解することが大事なのか?」
そんなふうに、相手の動機や立場に立って思考できるようになりました。
結果、チーム内でのコミュニケーションも円滑になり、プロジェクトの成果も安定して出せるようになったんです。
深掘り学習は“知識の終点”ではなく“思考の起点”
この学習法を続けるうちに、私は1つの確信を持つようになりました。
深掘り学習とは、「覚えること」をゴールにしない学び方。
むしろ、「問い続けること」をスタートラインにする思考法だと。
表面的な理解では、知識は一時的な“点”にしかなりません。
でも、「なぜ?」を繰り返すことで、その点は線となり、面となり、“自分の知識地図”として脳に定着していくのです。
そしてその地図は、新しい知識を吸収するたびに、どんどん広がっていきます。